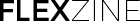マティアス・ベルドーモはウルグアイ生まれのシェフ。母国の軍事政権から逃れていた両親と共に、アルゼンチン、ブラジル、デンマークを渡り歩き、ウルグアイに帰国。14歳の時に退学し、趣味で通っていた料理教室を通して、料理の道に進むことを決心する。その後ウルグアイにあるイタリアンレストランのチェーン店にて、約40人をまとめるエグゼクティブ・シェフに若干18歳で就任するなど、彼の才能はすぐに頭角を現し、21歳の時にイタリアへ渡る。ミラノのレストラン「アル・ポン・デ・フェール」でシェフを務めると、それまで提供していた家庭的な料理からグルメ路線へと大きく転換した功績が認められ、2011年には同レストランがミシュランの一つ星を獲得。その4年後には、ミラノで自身初のレストラン「コントラステ」をオープンすると、その奇想天外な食材の組み合わせやプレゼンテーションは、ミラネーゼの間でも評判となり、予約が全く取れないほどの盛況ぶりとなる。2018年1月にオープンした新しいビストロ「エクシット」は、同年にミシュランの一つ星を獲得するなど、今イタリアで大注目のシェフ。
マティアス・ベルドーモはウルグアイ生まれのシェフ。母国の軍事政権から逃れていた両親と共に、アルゼンチン、ブラジル、デンマークを渡り歩き、ウルグアイに帰国。14歳の時に退学し、趣味で通っていた料理教室を通して、料理の道に進むことを決心する。その後ウルグアイにあるイタリアンレストランのチェーン店にて、約40人をまとめるエグゼクティブ・シェフに若干18歳で就任するなど、彼の才能はすぐに頭角を現し、21歳の時にイタリアへ渡る。ミラノのレストラン「アル・ポン・デ・フェール」でシェフを務めると、それまで提供していた家庭的な料理からグルメ路線へと大きく転換した功績が認められ、2011年には同レストランがミシュランの一つ星を獲得。その4年後には、ミラノで自身初のレストラン「コントラステ」をオープンすると、その奇想天外な食材の組み合わせやプレゼンテーションは、ミラネーゼの間でも評判となり、予約が全く取れないほどの盛況ぶりとなる。2018年1月にオープンした新しいビストロ「エクシット」は、同年にミシュランの一つ星を獲得するなど、今イタリアで大注目のシェフ。
ワカペディアの見るマティアス・ベルドーモ
ダークブラウンのくしゃくしゃなカーリーヘアの下に見える、ブルーのたれ目に口ヒゲを生やした男性。まるでその姿はシェフというよりも、シャワーから出たばかりのサッカー選手のようだ。ブルーのたれ目を見ると、一見少し頼りなさそうな雰囲気も感じ取れるのだが、料理の話を始めると一転、キリッとした表情になる。きっとラテン男が好きな女性にはたまらない、イケメンっぷりだろう。そんな彼は今年38歳になるが、まるで雲を指しながら「ねぇ、あの雲って○○みたいだね!」とでも言いそうな、夢を追いかける少年のような笑顔が特徴的だ。一体どんな人物か知りたくなったって?それでは、南アメリカからイタリアへ渡り、ミラネーゼ達の胃袋を鷲掴みした彼のインタビューを、さぁ召し上がれ!

ワカペディア:マティアス、久しぶり!実は、ワカペディアが一番はじめにインタビューをしたシェフがあなただったって、知ってた?前にもインタビューをさせてもらったけれど、ワカペディアのサイトはリニューアルしたし、相変わらずイケメンだからもう一度しちゃうね!今は二つのレストランを手掛けているけれど、昔からイタリアで活動をしようと思っていたの?
マティアス:Bueno!(いいよ!)なんでも話すよ。でも、頼むからイケメンって呼ばないでもらえるかな(笑)。本当のことを言うと、イタリアではなくてフランスに行って、オートキュイジーヌ(フランスの伝統的な高級料理)を学びたいと思っていたんだ。でも当時は誰のツテもなかったし、ウルグアイではシェフという職業はかっこいいとか、良い仕事と思われるようなステイタスでもなかったから、簡単ではなかったんだよね。そんな夢を捨てられずにいたある日、突然イタリア行きの話が舞い込んできて、何も考えずに即決したんだ。
ワカペディア:その選択は大正解だったね!こんなに才能がある素敵なシェフをイタリアが歓迎したなんて、イタリア出身者としてすごく誇りに思うよ!ところであなたが作る料理はとてもクリエイティブだけど、その創造性はどこから来るの?
マティアス:そうだね、やっぱりどんなことでも興味を持つことから始まるかな。怖さや疑問、不安や心配さえ、新しいものを生み出す研究要素の一つだと思うんだ。何とかしようって必死になるからね。あと僕はどんなことでも、使う材料やプロダクトの素材や生産地など、基本的なことから学ぶんだ。料理で大切なことは、味覚の記憶がどこまで人生の経験と結び付けられるかということだと思うよ。
ワカペディア:まるでフランスの作家・マルセル・プルーストの、「失われた時を求めて」に出てきそうな言葉だね。マティアスは、アートや文学からもインスピレーションを受けることはあるの?

マティアス:いい質問だね。今の時代はファッションやデザイン、アート、映画など、あらゆる分野でインスピレーションを得られると思うし、全てのものに参考点はあると思う。それが僕の料理では、ラザニア味のドーナツだったり、イチゴの形をした肉のタルタルであったり、LEGOの形をしたデザートプレートに姿を変えるんだよ。でも最近は、ただ見た目やインパクト重視の料理からは少し離れたいとも思い始めてきたんだよね。
ワカペディア:え、どうして?!マティアスの料理は一つ一つ遊び心があって面白いのに!もっと抽象的なテーマの料理を作りたいと思っているとか?
 マティアス:ははは!それも悪くないけど、どちらかというと、それならキュビズムをテーマにした料理の方が興味あるかな。360度の角度から見たものを一つの皿に表現してみるとか。今度はどんなテクニックを使うかわからないけれど、少なくともお客さんが食べた時、何を食べているかわかるものを作りたいね。アーティスティックに仕上げようと凝りすぎて、お客さんが一体何を食べているかわからなくなるというのは、避けたいかな。
マティアス:ははは!それも悪くないけど、どちらかというと、それならキュビズムをテーマにした料理の方が興味あるかな。360度の角度から見たものを一つの皿に表現してみるとか。今度はどんなテクニックを使うかわからないけれど、少なくともお客さんが食べた時、何を食べているかわかるものを作りたいね。アーティスティックに仕上げようと凝りすぎて、お客さんが一体何を食べているかわからなくなるというのは、避けたいかな。
ワカペディア:面白い話になってきたね!シェフ、ペルドーモの料理の哲学をもっと詳しく教えて!
マティアス:最近はね、材料や成分を顕微鏡で見ているんだ。例えばトマトを分子レベルで見て、顕微鏡で見たものをお皿の上で表現するんだよ。別にガストロノミー界を改革したいと思っているわけではないけれど、今はまだ試験的な段階とはいえ、自分がやりたいことに挑戦しているとこなんだ。
ワカペディア:なんだかまるで、ピカソにインタビューしてるみたい!「アル・ポン・デ・フェール」はすでにミシュランの星を獲得しているけれど、新しいビストロ「コントラステ」も、今年ミシュランの星を獲ったよね。おめでとう!
マティアス:なんだかミシュランの審査員みたいなこと言うね(笑)。あの日も審査員が、「おめでとう!星を獲得しました!」って言いに、店まで来たんだよな!(笑)
ワカペディア:そうなんだ!それで、その審査員にはなんて答えたの?Gracias (スペイン語でありがとう)?それとも嬉しすぎて泣いちゃったとか?
マティアス:それは・・・Grazie(イタリア語でありがとう)!って、もちろん言ったさ!仲間と抱き合って泣くような青春ドラマみたいなリアクションはしなかったけど(笑)。
ワカペディア:そうだったんだね(笑)!そんなマティアスは、ミシュランの星自体についてはどう思っているの?
マティアス:僕はミシュランの星が全てだとは思わないね。だって、星がなくても輝いているレストランは沢山あるだろう?確かに星は、多くのシェフにとってすごく満足感を与えるものであるし、周りの人々に影響を与える一種の「報告」であると思う。でもシェフは、レストランのエンジンであり、魂でもあるべきなんだ。だから僕にとって、ミシュランの星を取るために頑張らないといけないと考えるのは、なんだかとても浅い考えに感じるんだよね。
ワカペディア:そうだね。多くのシェフがミシュランの星の獲得を目指す中、過去には星を返上するシェフもいたよね?
マティアス:そうだね。フランス人シェフのセバスチャン・ブラス氏は、過度のメディア露出やストレス、プレッシャーから、1999年に三つ星を返上したんだよ。残念なことに、彼にとって星は、名誉な事というよりも、仕事への障害となってしまったんだ。彼の決断を通して僕が考えさせられたことは、自分がミシュランの星に影響を受けるのではなく、自分が自身の才能や創造性を、他人へ影響を与えていかないといけないということさ。

ワカペディア:Wow !イタリアンのシェフから、こんな風に人生の哲学を教わるなんて思ってもいなかったよ!(感心するワカペディア)
マティアス:別に、当たり前の事を言っているだけだよ(照笑)。それに、自分がどう世間で見られているかっていうのも、実際はどうでもいいことだと思うんだ。それを常に意識していると、自分の存在感ばかりを気にするようになって、料理の楽しさ自体を忘れてしまう気がするからね。
ワカペディア:確かにそうだよね。・・・でもマティアスは、ミシュランの星を返上したいとは思っていないでしょう?(笑)
マティアス:それはまた別の話だね(笑)僕が言いたいのは、ミシュランの星を獲得できた事自体はすごく嬉しいけれど、その星の数や華やかなショーによって自分の人生が窮屈なものになったり、自分自身を見失うのは嫌だっていう事なんだ。今年はいくつかの賞を受賞したけど、賞そのものよりも僕の料理を食べてくれるお客さんの方が大切だし、彼らがレストランを出る時に、どんな気持ちで席を立っていくかの方が、興味あるよ。
ワカペディア:まさにそうだね!
マティアス:僕にとって料理とは、労働じゃなくてパッションそのものなんだ。
ワカペディア:どのシェフもそういう思いでいてくれればいいのだけれど・・・でも、もう何十年もシェフをしていたら、そのパッションが尽き果てることはないの?
マティアス:パッションはね、与えなければなくなってしまうものなんだよ。どんなことでも全てがバラ色に進むことなんてないし、深いコミットメントと犠牲が必ず伴うんだ。例えパッションがあったとしても、常にそれを自分だけで楽しむのではなく、社会のために貢献するものとして扱わなければいけないんだよ。
ワカペディア:さすがマティアス!今日のインタビューで更にあなたの料理に対する哲学がわかったよ。このまま頑張って夢を追いかけてね!
マティアス:大丈夫、僕は歳をとるほど若くなっていくから!(笑)

Description & Interview: Sara Waka
Edited by: Yurie. N
Foto: Ivan Grianti