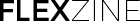日本製の革靴を世界に発信する「HAKIMONO」プロジェクトが、日本の誇る革靴職人とサステナビリティを応援!
日本経済産業省による支援の元、2017年にスタートした「HAKIMONO」は、高い職人技術と伝統文化が融合した日本の革靴を、国際的に広めるプロジェクトだ。
日本で革の加工は武士の時代から始まり、元は刀や鎧などの鞘(さや)に使用されていた技術が、引き継がれつつ時代に合わせて変化してきた。「HAKIMONO」が支援している多数のブランドも、高品質な素材と革新的なデザインへの変化だけでなく、環境問題を意識した方法での靴づくりを試みている。今回は、そんなサステイナブルな方法で革靴を製造している4ブランドをご紹介しよう。
天然皮革の美しさと独自性を追求した「H. Katsukawa」のニベ革
通常は皮の裏側にある脂肪や肉を指し、食品に使われることが多いニベ革。それをデザイナーの勝川永一氏が独自に開発し、特に製造過程では環境に配慮しながら、革靴へと変身させた。「H. Katsukawa」のニベ革シューズは、汚染化学染料の使用を避けるというこだわり通り、靴は自然な形と素材で、どの季節でも快適に履けるのが特徴だ。
また、2010年には東京・目黒区に「The Shoe of life」というショップをオープンし、革靴のアフターサービスや修理サービスを提供するなど、消費者が長期で使用できるよう配慮している。その質とデザイン性の高さを武器に、厳選されたスーツや革靴などが集められる世界最大のメンズファッション展示会「ピッティ・ウオモ」では、ポップアップストア招待デザイナーとして7回参加した。まさに独自性、耐久性、デザイン性、そしてサステナビリティを兼ね備えた「H.Katsukawa」の靴は、海外からも注目されている。

ブランド情報 : http://www.nibe-leather.com/profile/
オンライン販売 (JOOR) : https://www.jooraccess.com/hkatsukawa
インタビュー : https://www.youtube.com/watch?v=hBYe-Cl8jrE
「Studio Imago」による何度でも修理可能な革靴と、ワンランク上のリサイクル
Studio Imago社が手がける、「Hiroshi Kida」と「+ SOLE(ADDITIONAL SOLE)」という2つのブランド。
デザイナー兼創設者である、木田浩史氏の名前がつけられた「Hiroshi Kida」の革靴は、一から全て職人の手で作られている。主にイタリアの高級靴の分野で使用される「ブレイク」と呼ばれるイタリアの伝統的な加工技術を使用していて、木田氏がこの製造法にこだわる理由は、靴全体または一部が損傷した場合、何度でも修理することが出来、他の製造方法で作った革靴よりも長く使えるためだ。「+ SOLE(ADDITIONAL SOLE)」もサステナビリティに配慮しており、ただ修理をするだけでなく、新しい高品質のソールを追加することで、使い古した靴をワンランク上のものにするという、特徴的なリサイクルの手法をとっている。
どちらのブランドも、これまで主要だった大量生産型のファストファッションとは対照的なアプローチだ。日本の伝統技術を用いながら、植物由来で環境に優しい染料や、より高品質で耐久性のある素材を追求し続けることで、消費者が長く使い続けられる商品の開発を目指している。

ブランド情報 : https://www.instagram.com/studioimagohiroshikida/
オンライン販売 (JOOR) : https://www.jooraccess.com/hiroshikida
インタビュー : https://www.youtube.com/watch?v=ZlFzYiy-_4U
独創的で環境にやさしい型破りな革靴「Numero Uno」
大山一哲氏がデザインする「Numero Uno」は、珍しいふぐ革を使用しているのが特徴だ。多くのふぐ革が廃棄される中、ファッションにはほとんど使用されない素材を取り入れることで、環境への影響を減らすことが、大山氏の目的だ。この他にも、Numero Unoは非従来型の革で様々なモデルを開発してきた。他の例が、鹿革(バックスキン)のコレクションだ。
ここ数十年、皮革の使用と鹿肉の消費が大幅に減少した事で増殖し、他の動物種に悪影響を及ぼしてきた野生のダマジカ。状況を憂慮した住民が再び消費するようになったが、革に関しては、これまでファッション業界では、革の面積が小さすぎるという理由から、ほとんど使用してこなかった。大山氏はこの問題への解決策として、余った鹿革を再利用し、革の特性に合わせたコレクションを発売した。また大山氏は、牛革に比べて脆弱という鹿革の最弱点を強化すべく、インディゴ染めのバックスキンの開発にも取り組んでいる。大山氏の目標は、環境への影響が少ない天然素材を再利用し、洗練されたデザインと組み合わせることで、エコロジーとファッション業界の永続的なバランスを見いだす事である。

ブランド情報 : https://www.instagram.com/numero_uno_io/
オンライン販売 (JOOR) : https://www.jooraccess.com/numerouno
インタビュー : https://www.youtube.com/watch?v=9NLOysMEUAA
「Kyoko Sasage」の100%土に還る和紙と革靴
日本が誇る伝統工芸の一つである和紙は、繊維が長いため、ヨーロッパの紙よりも細くて強い。従来の方法で作られた和紙は、2014年にユネスコの無形文化遺産として登録され、現在も折り紙、書道、浮世絵だけでなく衣類に至るまで、様々な用途で使用されている。
エコな取り組みが加速化したファッション業界にとって、和紙は自然由来の素材で耐性があるため、環境汚染を促進する化学繊維への代替品として期待されている。
デザイナーの捧 恭子氏はイタリアで靴作りを学び、日本に帰国してブランドを設立。日本の伝統的な技法を用いて、革の職人技に和紙を組み合わせた独自の靴づくりを行なってきた。捧氏の革靴は、通気性と抗菌性に優れた素材を裏地に使用しているため、素足での履き心地も抜群だ。さらに、「Kyoko Sasage」による和紙と革靴は100%天然素材で製造しているため、環境を汚染することなく土に還るようにできているのが特徴だ。デザインには、日本人女性らしい、移り変る季節や自然を愛でるような、繊細な植物のモチーフ(花、植物、果物など)が取り入れられている。

ブランド情報 : http://belpasso-acs.info/
オンライン販売 (JOOR) : https://www.jooraccess.com/kyokosasage
インタビュー : https://www.youtube.com/watch?v=guREJOFR9KM
以上が、日本発の革靴4ブランドだ。新型コロナウイルスの影響により、一層デジタル化が進んだ「HAKIMONO」プロジェクトは、現在トレードショーやセレクトショップまで展開する「Man / Woman」のサイト上、そして、大手B2Bのオンラインプラットフォーム、「Joor」にて、セールスキャンペーンを開催している。もっと詳しく知りたい方は、是非サイトをチェック!(2021年2月末まで)